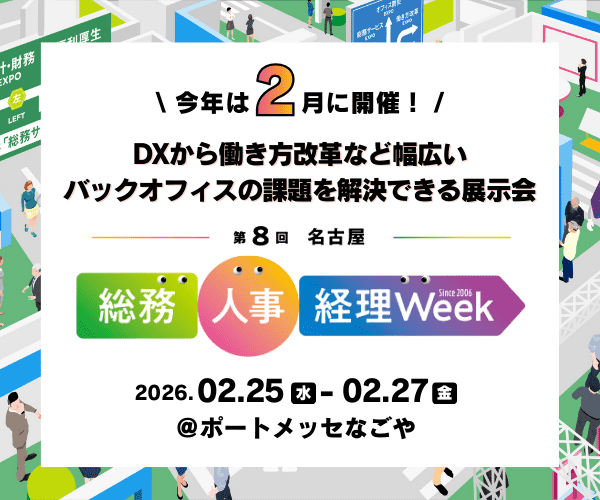アクセスランキング
手待ち時間とは、通常は作業と作業の間の労働に従事していない時間をいう。待機時間とは始業時刻から終業時間の間の拘束時間中ではあるが、労働はしておらず、次の労働に備えて準備している時間をいい、外形的には仕事に従事せず、休んでいる時間である。手待ち時間や待機時間が休憩時間に該当するなら、労働時間にならない。手待ち時間や待機時間が、労働基準法(以下、労基法)上の労働時間になるのか、休憩時間と取り扱われるのかでは、労働時間の法令上の制限や賃金、割増賃金支払い義務の関係などで重要な問題となる。
労基法における労働時間とは?
拘束時間中ではあるが、現に作業や業務に従事していない時間が、休憩時間と認められる場合ならば労働時間にならない。
そこで、その時間が労働時間か休憩時間か、どちらに判断されるのかがポイントとなる。労基法上は「休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと」(昭22.9.13 基発17号)とされている。
このため、労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたと評価される時間を指すものであり、そのように評価される時間であれば、必ずしも現実に精神または肉体を活動させていることを要件とはしない。要するにその時間が労働者にとって権利として労働から離れることが保障され、現にそのように取り扱われているか否かが判断基準となる。判例上も労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」(平12.3.9 最高裁一小判決)とされている。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。