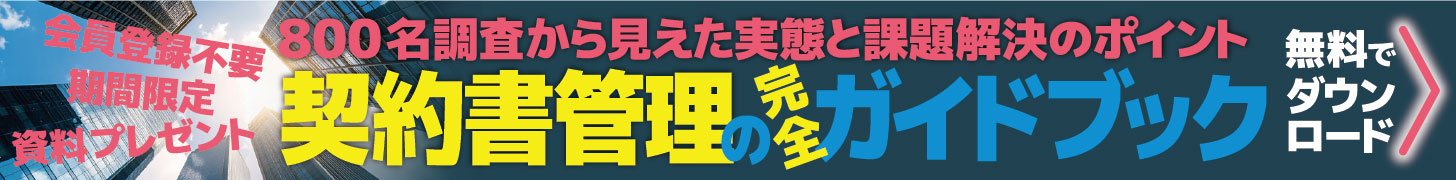なぜバイアスを防ぐための「面接チェックシート」が逆効果に? 採用選考での評価を公正にするには

アクセスランキング
採用活動において応募者の適性や能力を見極めることはとても重要な機能です。しかし、人が人を見立てるという行為には、どうしてもバイアス(先入観や思い込み)が伴います。採用担当者や面接官は、事前に研修を行ってもなかなか排除することはできないバイアスの存在を前提とし、「自分の見方は偏っているのではないか」という自覚を常に持ち続けることが肝要となります。
人の評価をゆがませる心理的傾向
バイアスは、選考の公正さを大きく損なう可能性があります。
代表的な例として、まず挙げられるのが「類似性効果」です。これは、人は自分に似たタイプの人に親近感を持ちやすく、結果として高く評価しがちになるという傾向です。そして、初対面の応募者に対して第一印象などで一度人物像を認識してしまうと、そのあとは、その認識を裏付けるような情報ばかりを集め、反対の事実には目を向けなくなる傾向を指す「確証バイアス」。さらに、応募者の持つ一部分の属性、たとえば容姿や学歴といった特定の要素に引きずられ、まるで後光が差したかのように全体が実際以上に優れて、あるいは劣って見えてしまう現象が「ハロー効果(後光効果)」です。欧米では、このハロー効果を打ち消すために、求人の際に写真の添付や年齢、名前さえ事前には知らせないといった対策が取られることがあります。
また、複数の応募者を一斉に評価する際に、優秀な応募者とそうでない応募者を比較することで、その違いが実際以上に際立って感じられてしまう「対比効果」も、相対評価の際に注意すべきバイアスです。そして、面接官が応募者に対して「将来有望な人材だ」といった「期待」を持つと、それが実際に良い結果(成績向上など)を生み出す「ピグマリオン効果」や、逆に「劣っている」と決めつけられることで悪い結果が生じる「ゴーレム効果」といった、期待が評価に影響を与える現象も存在します。
これらのバイアスについて知り、自分がどのような傾向を持っているかを確認することは、「人を見立てる力」を高める上で不可欠なのです。
面接チェックシートがはらむ問題
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。