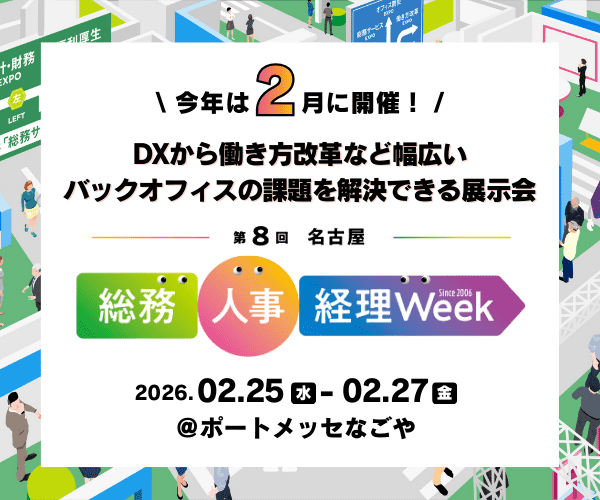アクセスランキング
『月刊総務』で実施した「企業文化に関するアンケート調査」では、回答者の約9割が企業文化のアップデートは重要なことであり、自社の企業文化に関してもアップデートが必要だと回答しています。今回は、企業文化のアップデートに向けて、何を検討し、何から着手すればよいのか、そのポイントを紹介します。
企業文化とは?
企業文化と近い言葉として、組織文化、企業風土、社風などがありますが、これらの言葉について、一般的に広く定着している定義や整理は残念ながら存在しないといってよいでしょう。
企業文化について比較的よく知られている定義としては、組織論の第一人者といえるエドガー・シャインによるものがあります。シャインは「ある特定のグループが外部への適応や内部統合の問題に対処する際に学習した、グループ自身によって、創られ、発見され、または、発展させられた基本的仮定のパターン」と定義した上で、企業文化には「階層」があるとしています。ここでいう階層とは、以下の3つを指します。
(1)目に見えるもの(例:服装、レイアウト、言葉遣いなど)
(2)言葉になっているもの(例:理念、経営メッセージなど)
(3)無意識のもの(例:思い込み、信念、体質など)
たとえば、経営方針や経営層メッセージで「顧客志向」や「家族経営」を繰り返し訴えている企業があるとしましょう。経営理念も見直して顧客志向や家族経営に関連する内容を入れ、社内ポスターやカルチャーブックを配布していたとします。ところが、社内会議で経営・事業のさまざまな意思決定をする場面では、「顧客志向」や「家族経営」というよりは売り上げ至上主義や、コスト削減最優先、まるでやりがい搾取のような議論・判断・意思決定をしている場合があります。これは、このような文化があまりにも日常になっており、そうなってしまっていることすら無自覚なためです。
この場合、経営方針や経営層メッセージで特定のメッセージを訴えていること、経営理念にも関連する内容を入れていることは「(2)言葉になっているもの」に相当します。ポスターやカルチャーブックの配布は「(1)目に見えるもの」、自社の文化に無自覚であることは「(3)無意識のもの」です。
企業文化を変革するためには、この「(3)無意識のもの」を変化させる必要があります。表層的な「(1)目に見えるもの」や「(2)言葉になっているもの」を変えただけで企業文化をアップデートできたと考えてしまいがちですが、根源的には体質が変わっていないことは少なくありません。もちろん、それらを変えることで、徐々に変わっていく部分もあります。大切なことは、「(1)目に見えるもの」や「(2)言葉になっているもの」と「(3)無意識のもの」に、乖離がないか、乖離によって従業員がストレスを感じていないかを確認しながらアップデートを進めていくことです。
企業文化の変革、何から着手する?
あまりにも本質的・根源的な話をしたので、企業文化の変革に向けて「重いな……」と感じた方がいるかもしれません。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。