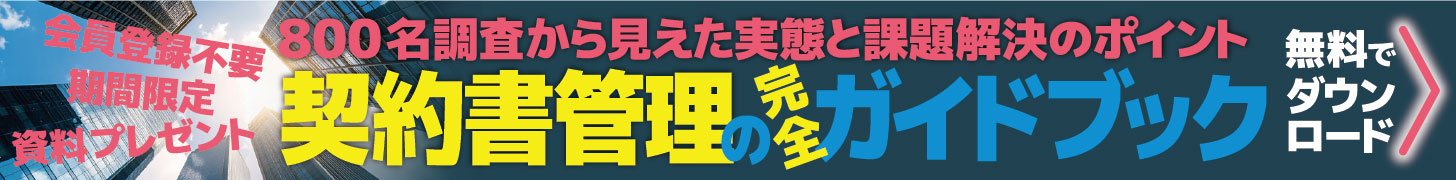アクセスランキング
筆者は、インターナル・コミュニケーションの支援を行うウィズワークス株式会社が主催する社内報の企画コンペティション「社内報アワード」の審査員を2017年から務めています。この7年、コロナ禍やデジタルツールの使用環境など、インターナル・コミュニケーションを取り巻く状況が大きく変化してきました。今回は、長年審査員を務めてきた経験を踏まえ、社内広報の3つのトレンドをご紹介します。
(1)トップメッセージの変化
トップメッセージは、古くから定番コンテンツです。発信時期は年頭あいさつや年度初め、株主総会後、内容は経営状況の振り返りと経営方針、従業員に意識・実践してほしいことを盛り込む場合が多いでしょう。この7年の間に新型コロナウイルス感染症によるリモートワークの実施や社内のITインフラの変化に伴い、トップメッセージが大きく変わりました。
トップメッセージを全社共有する手法として、かつては社内報冊子が中心であり、年に2、3回程度、トップの所信を載せていました。ほかの手法を用いた例は必ずしも多くなかったのです。もちろん、社内報冊子に加えてイントラネットやWeb社内報にも載せることはありましたが、同じ内容を再掲したり、アーカイブしたりするものが少なくありませんでした。
しかし、この数年、社内報冊子やWeb社内報、動画、音声などさまざまなツールと表現形態でトップメッセージが発信されるようになっています。たとえば社内報冊子は公式的な所信表明、Web社内報はトップの普段のようすの紹介といったフランクな内容、動画や音声では経営方針に対する従業員への質疑応答などと使い分けているようです。
このほか、経営層と従業員の対話形式のイベントを実施する企業が増えている印象です。社内報アワードの審査基準にも「経営と現場の心理的距離を短縮する」「経営方針を浸透させる」といったものがあります。新型コロナウイルス感染症を経て、経営層が従業員に対して「メッセージを発信すること」の重要性に気付いたように思います。同時にそのためには、手を替え品を替えメッセージを発信し続けなければ想いを浸透させ切れないことにもです。
こうした変化はとても良いですが、一方、従業員に対して指示的・命令的なメッセージがあふれてしまっていないか注意する必要があります。そうしたメッセージばかりでは、経営と現場の心理的距離は縮まらないですし、経営方針に対する反発感情も生まれやすくなります。本来の狙い・目的は何かを社内広報を担当する総務スタッフがしっかりと考え、場合によっては経営トップにメッセージの内容変更を進言するようにしましょう。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。