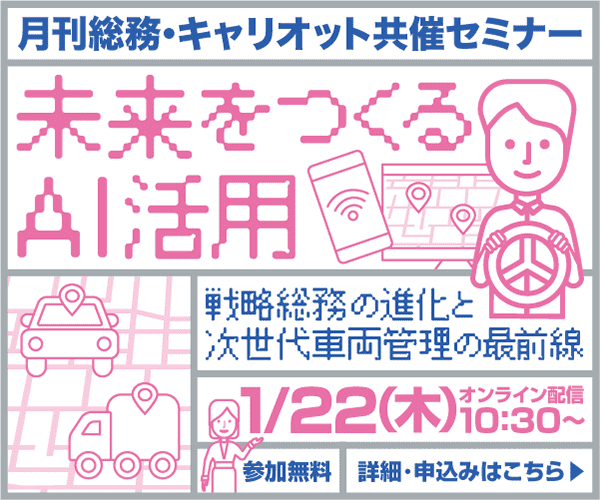アクセスランキング
来年度の広報予算・計画の検討時期ということもあり、前回は「広報戦略」とはそもそもどのような概念なのかについて扱いました。ポイントをおさらいしておくと、広報活動の原理原則は「態度変容」であり、それには認識〈(1)知名・(2)認知・(3)評価〉、感情〈(4)情動・(5)意欲〉、行動〈(6)行動〉という3つの構成要素があります。この原理原則を踏まえて、「ステークホルダーと良好な関係の構築・維持をはかるために、意図的・計画的にステークホルダーの態度変容の実現を目指すもの」が広報戦略の定義であり、経営・事業活動上、態度変容の(1)~(6)の何を重点的な課題として、いつまでに、どうやって(情報の受発信の具体的な内容)、底上げをしていくかを明文化したものだとお伝えしました。
ただし、こうした「広報戦略」では、危機管理広報の扱いは宙に浮くことがありますし、ここまでの戦略性が求められない、または、戦略性を描きにくい組織・企業もあります。この場合は、「広報方針・計画」の策定が必要になります。
戦略性が求められながらも、戦略に特化しにくい広報の難しさ
一般的に「戦略」とは、何をやり、何をやらないかを明確にするものといわれます。たとえば、経営・事業活動上の課題として、「自社の代表的なサービスの知名度や認知は一定程度あるものの、他社のサービスと差別化できていない」状況だったとしましょう。仮に差別化し得るポイントが「技術力の高さ」だとすると、「技術力が高いという評価を得るための広報活動を行う」ことが戦略の基本指針となります。
この場合、一般的な考え方の「戦略」としては、技術力の高さに関する情報発信を行い、技術力の高さの訴求につながらない情報発信は行わないことになります。戦略とは、集中的に資源を投入して、確実に成果を得ようとするものであるためです。しかし、本当に「技術力の高さ」の訴求に絞ることはできるのでしょうか。新サービスが出たり、経営から何らかのサービスに関する情報発信強化の指示があったりすれば、そちらの情報発信が優先になります。このように広報活動は、戦略性が必要でありながらも、戦略だけに特化しにくい現実があるのです。
社内広報を担当している場合、社外広報の領域についてはイメージがわきにくいかもしれません。そこで、社内広報の領域でも例示してみましょう。たとえば、「従業員エンゲージメントの高さと職場内の良好な人間関係に相関がある」ことが明確になったとします。このとき、社内広報としては、職場内のコミュニケーションの在り方や好事例を積極的に扱うことが必要になりますが、実際はこの内容ばかりに偏らせることはできません。経営メッセージの発信や、各事業・製品・サービスの紹介も必要です。歴史を扱うことも重要かもしれません。社内広報にも戦略的な視点は必要ですが、一般的な戦略論のように、特定の情報発信に特化することは難しい側面があるのです。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。