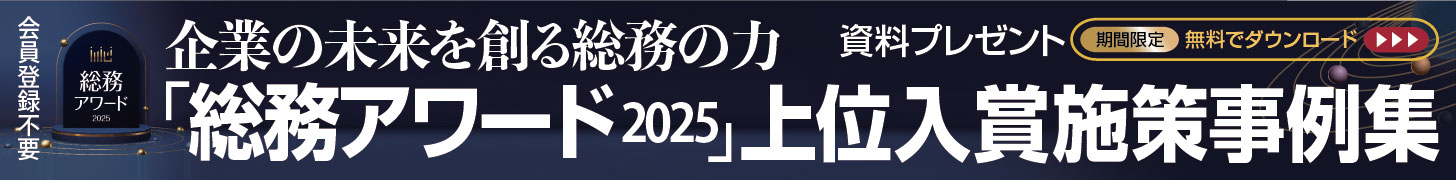アクセスランキング
前回は、働き方の多様化が進む中で増加してきた柔軟な働き方の一つであるスポットワークについて取り上げた。今回は、同じく柔軟な働き方として社会に普及してきたフリーランスをテーマとして扱う。
個人であるフリーランスと組織である発注事業者との間には交渉力などの格差があり、フリーランスが取引上弱い立場にあることから、報酬の不払いやハラスメントといったさまざまな問題やトラブルが発生している。そこで、2024年11月1日にフリーランスが安心して働ける環境を整備するためにフリーランス・事業者間取引適正化等法(以下「フリーランス法」という)が施行された。本稿では、取引の適正化や就業環境の整備など、フリーランスを活用するにあたって留意しておくべき事項をおさらいする。
フリーランス法の対象となる事業者は?
フリーランス法の対象となる「特定受託事業者」(以下「フリーランス」という)とは、業務委託の相手方である事業者であって、(1)個人であって、従業員を使用しないもの、(2)法人であって、代表者以外にほかの役員がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものをいう。なお、労働者が副業としてフリーランス事業を行う場合もこれに該当する。一方で、形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、フリーランス法は適用されない点に留意が必要である。
「業務委託事業者」(以下「発注事業者」という)とは、フリーランスに業務委託をする事業者をいい、フリーランスも含まれる。発注事業者のうち、(1)個人であって、従業員を使用するもの、(2)法人であって、2以上の役員がいる、または従業員を使用するもののいずれかに該当する発注事業者を「特定業務委託事業者」といい、特定業務委託事業者にはフリーランスは含まれない。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。