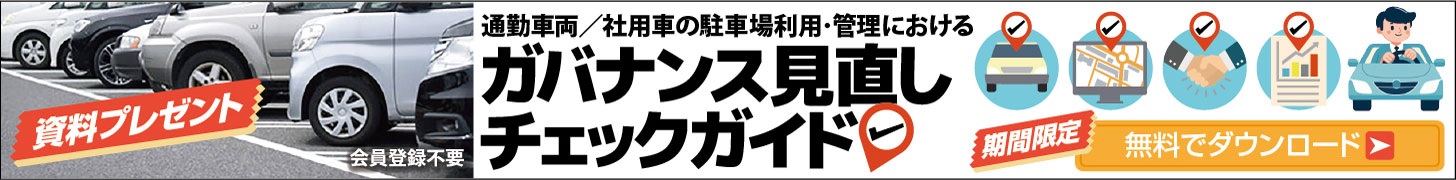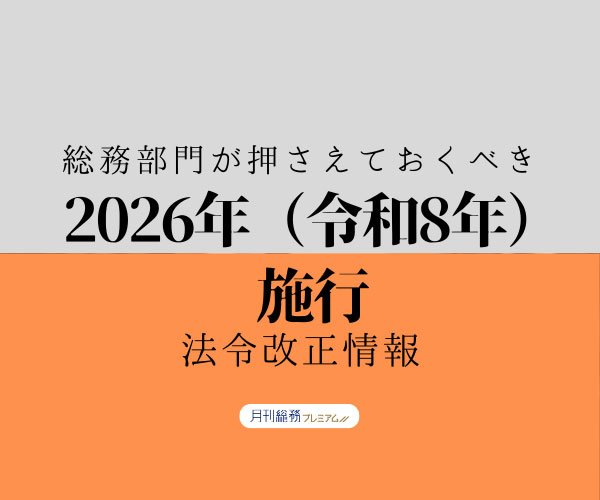就業規則、労使協定、労働協約の違いを説明できる? 労働に関するルールにおける優先順位は……?
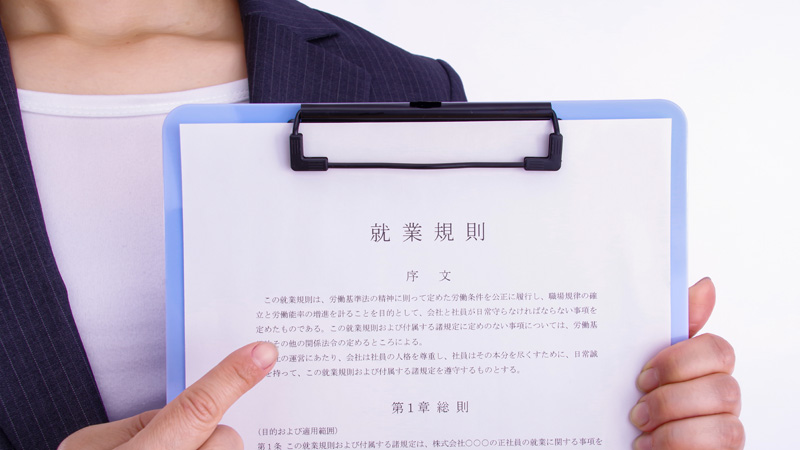
アクセスランキング
社員が会社で働くルールといえば、就業規則を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、これ以外にも労使協定と労働協約があります。それぞれの特徴とルールの優先順位について確認してみましょう。
労使協定の種類と具体的な活用例
労使協定は、使用者(企業)と労働者代表(事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は当該労働組合。事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の間で取り交わされる書面契約です。労働基準法等の枠内を超えた働き方を、労働者と使用者の双方同意の上で、一部法令の適用除外とすることを目的としています。労働者の権利を守りつつ、企業の運営を円滑にする役割を果たしているといえます。
労使協定にはさまざまな種類があり、企業の運営や労働者の働き方を柔軟にするために活用されています。具体的な例として以下のようなものがあります。
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)
なじみのある労使協定の一つではないでしょうか。法定労働時間を超えて労働させる場合に必要な協定です。1年ごとに協定を締結して、労働基準監督署への届け出が必要です。
1か月単位の変形労働時間制に関する協定
1か月の範囲内で労働時間を調整し、繁忙期と閑散期に応じた勤務時間を設定するための協定です。
フレックスタイム制に関する協定
労働者が始業・終業時刻を自由に決められる制度を導入するための協定です。
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定
たとえば外回りの業務が多い職種など、労働時間の全部または一部を事業場外で従事した場合で、使用者の具体的な指示が及ばず、労働時間が算定しにくいときに一定の労働時間をみなし労働時間として扱うための協定です。
賃金控除に関する協定
労働者の給与から社宅費や組合費などを控除する場合に必要な協定です。
労使協定が企業に与える影響
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。